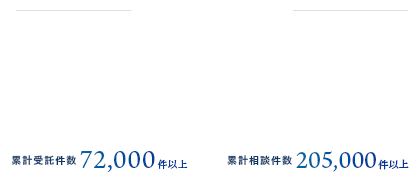空き家の特例について徹底解説!
2021.07.28特例の概要
相続または遺贈により取得した被相続人の不動産を、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から相続人一人あたり最高3,000万円まで控除することができるという制度です。【具体例】
売却価額:5000万円
取得費不明 ※取得費が不明の場合は売却価額の5%で計算します
諸経費:200万円
●特例が適用されない場合
(5000万円(売却価額)―250万円(取得費)―200万円(諸経費))
×20.315%(税率)=924万円
●特例が適用される場合
×20.315%(税率)=924万円
(5000万円(売却価額)―250万円(取得費)―200万円(諸経費)
―3000万円)×20.315%(税率)=314万円
―3000万円)×20.315%(税率)=314万円
上記からも特例が適用されると610万円もの税金を減額することができます。
特例の対象
相続または遺贈により取得した被相続人の不動産と一言でいっても全てが当てはまるわけではありません。下記の要件に全てに当てはまっている不動産が対象となります。被相続人居住用家屋について
被相続人居住用家屋とは、相続の開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた家屋のことを指します。具体的な要件として、下記の3つ全てに当てはまっていなければなりません。
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいなかったこと
被相続人居住用家屋の敷地等について
被相続人居住用家屋の敷地等とは、相続の開始の直前(従前居住用家屋の敷地の場合は、被相続人の居住の用に供されなくなる直前)において被相続人居住用家屋の敷地の用に供されていた土地又はその土地の上に存する権利のことをいいます。なお、その土地に2つ以上の建物があった場合、一体として自宅として利用していたとしても、主として居住の用に供されていた家屋のみが控除の対象となります。そのため、土地については、地積に控除対象の家屋の床面積割合を乗じた部分のみが対象となります。
また、相続した後に被相続人居住用家屋の全部の取壊した場合でも、その土地については被相続人居住用家屋の敷地等に該当します。
適用条件
前章に記載した不動産に対して、特例を受けるためには下記の条件を満たすことが必須です。- 売却した個人が、相続または遺贈により不動産を取得していること
- 売却する不動産について
- 相続開始から売却まで利用していないこと(貸付、居住していないこと)
- 売却時に一定の耐震基準を満たしていること
- 家屋を取壊している場合は、取壊しから売却までその土地に建物を建てていないこと
- 相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 売却代金が1億円以下であること
- 重複して受けられない他の特例の適用を受けていないこと
- 親子や夫婦など特別の関係がある人に対して売ったものでないこと
注意点
適用条件に加えて注意しなければならない点が2つあります。- 共有で取得する場合、それぞれ3000万円ずつ控除の対象となりますが、仮に土地と家屋を別々で取得する場合は適用が受けられないこと
- 相続税の取得費加算の特例は選択適用であること
適用を受けるための手続き
適用を受けるためには、下記の区分に応じてそれぞれに掲げる書類を添付して確定申告をすることが必要です。家屋または敷地等を売却した場合
- 譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕
- 売った資産の登記事項証明書等で次の3つの事項を明らかにするもの
- 売った人が不動産を被相続人から相続又は遺贈により取得したこと
- 昭和56年5月31日以前に建築されたこと
- 区分所有建物登記がされている建物でないこと
- 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
- 耐震基準適合証明書又は建設住宅性能評価書の写し
- 売買契約書の写しなどで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの
被相続人居住用家屋の全部の取壊し等をした後に売却した場合
- 前章の1、2、5で掲げた書類
- 売った資産の所在地を管轄する市区町村長から交付を受けた「被相続人居住用家屋等確認書」
まとめ
今回ご紹介した空き家の特例は、大きく減税できる魅力的な特例である一方で、添付書類が必要で、そもそも特例を使えるのか判断が必要な難しい制度です。不動産を相続するにあたって、空き家の特例を適用させる他にも、様々な検討事項があり、それぞれにメリット・デメリットがあります。不動産は税金の金額を大きく変える資産ですので、空き家の特例を検討される場合は、専門家へ相談することをお勧めします。