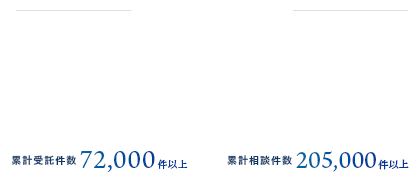生前贈与にかかる税金の節税対策ポイントと相続税の違いを解説
2023.03.03
相続税は亡くなられた親などからの財産が相続人に受け継がれる場合にかかる税金ですが、財産が多ければ多いほど、その分相続税の負担も大きくなります。そのため、生前対策として贈与を検討されている方も多くいらっしゃるのではないでしょうか。
しかし、贈与税の仕組みを理解していないと、贈与したとしても生前対策の効果が薄れてしまい、本来より多く納税してしまう可能性があります。
そこで今回は、贈与税の基本的なところから相続税との関係についてご紹介します。
事前に財産を贈与することで、自分が亡くなった際の財産(相続財産)が少なくなるため、将来負担すべき相続税を軽減することができる可能性があります。もちろん生前贈与の場合でも、一定の金額を超えれば贈与税が発生します。
また、贈与税とは、個人から財産を受け取ったときにかかる税金です。財産を受け取るだけではなく、債務を免除される等の利益を受けた場合も贈与税の対象となります。
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があり、同じ贈与税でも税率や基礎控除額等、違いが多くあります。
税率は最低10%から最高55%までの超過累進税率を採用しています。
この場合の贈与税の額は、財産の価額の合計額から、複数年にわたって利用できる特別控除額の2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
また相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例を適用することができなくなります。どちらが適しているか、それぞれのメリット・デメリットを理解し、十分検討しましょう。
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
次に、税率の違いです。どちらも、最低10%から最高55%までの超過累進税率を採用していますが、贈与税の方が課税される最低限度額も低く設定されていて、税率の累進性も相続税率より急になっています。
【贈与税】(直系尊属から成年へ)
【贈与税】(上記以外)
【相続税】
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
出典:国税庁「相続税の税率」
(特別控除額:2,500万円)
まず、加算対象となる贈与財産が違います。
暦年課税制度では、相続開始前3年以内に贈与された財産のみが加算対象となります。
一方相続時精算課税制度では、相続時精算課税を選択した年以降の贈与財産全てが加算対象です。
2点目の違いは、適用対象者です。暦年課税制度では、相続や遺贈により財産を取得した場合のみ適用となるのに対し、相続時精算課税制度では、たとえ相続放棄したとしても、適用対象となります。
例えば、暦年課税制度を活用したい場合は、
相続時精算課税制度を活用したい場合は、
死亡した時点での遺産額が課税対象の相続税は、遺産額やそれに基づく税金を自由に決めることができません。それに比べて贈与税は、どのくらい贈与するかを自由に決めることができますから、税負担を比較しながら毎年の贈与額を決定することができます。
相続税についてお悩みの際は、ぜひ一度弊社へご相談ください。
税理士法人NCPへのご相談はこちら
今回だけの相続税対策を考えず、将来を考えた生前対策をおすすめします。
生前対策をお考えの方、相続税について相談したい方は、ぜひ税理士法人NCPにご相談ください。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きている間に自身の財産を他者へ渡すことを指します。事前に財産を贈与することで、自分が亡くなった際の財産(相続財産)が少なくなるため、将来負担すべき相続税を軽減することができる可能性があります。もちろん生前贈与の場合でも、一定の金額を超えれば贈与税が発生します。
贈与税とは?
贈与税を理解する上で重要なことは、贈与は一方的な意思だけで成立するものではないということです。贈与する人とされる人との間で、あげた・もらったことを認識していないといけません。また、贈与税とは、個人から財産を受け取ったときにかかる税金です。財産を受け取るだけではなく、債務を免除される等の利益を受けた場合も贈与税の対象となります。
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」の2種類があり、同じ贈与税でも税率や基礎控除額等、違いが多くあります。
暦年課税制度とは?
1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与の財産額の合計から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に税率を乗じて計算されるものです。税率は最低10%から最高55%までの超過累進税率を採用しています。
相続時精算課税制度とは?
贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母または祖父母からその年の1月1日時点で18歳以上の子または孫に対して財産を贈与した際に、この制度を選択することで適用されるものです。この場合の贈与税の額は、財産の価額の合計額から、複数年にわたって利用できる特別控除額の2,500万円を控除した後の金額に、一律20%の税率を乗じて算出します。
| 暦年課税制度 | 1月1日から12月31日の1年間で受け取った贈与額の合計から、基礎控除額の110万円を差し引いた金額に税率を乗じて計算される制度 |
|---|---|
| 相続時精算課税制度 | 原則60以上の父母または祖父母から18歳以上の子どもや孫へ贈与する際に選択できる制度 |
生前贈与の節税対策メリット・デメリット
暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを使って贈与するのが有利になるのか、メリットとデメリットを比較して考えていきます。| 生前贈与 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 暦年課税制度 |
|
|
| 相続時精算課税制度 |
|
|
また相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例を適用することができなくなります。どちらが適しているか、それぞれのメリット・デメリットを理解し、十分検討しましょう。
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
相続税と贈与税の違い
一つ目は基礎控除額です。相続税は最低でも3,600万円で、相続人が1人増えるごとに600万円ずつ基礎控除額が加算されていきます。一方で贈与税は、財産額に関係なく受贈者1人につき年間110万円と決まっています。次に、税率の違いです。どちらも、最低10%から最高55%までの超過累進税率を採用していますが、贈与税の方が課税される最低限度額も低く設定されていて、税率の累進性も相続税率より急になっています。
【贈与税】(直系尊属から成年へ)
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万以下 | 10% | ― |
| 4,500万円超 | 55% | 640万円 |
| 基礎控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 200万以下 | 10% | ― |
| 3,000万円超 | 55% | 400万円 |
| 法定相続分に応ずる取得額 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 1,000万円以下 | 10% | ― |
| 6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:国税庁「贈与税の計算と税率(暦年課税)」
出典:国税庁「相続税の税率」
相続税と相続時精算課税制度に基づく贈与税の違い
暦年課税制度と同様に税率が違っています。また、相続時精算課税制度での控除額は、一度の贈与で使い切ってしまうものではなく、複数年にわたり利用でき、相続時精算課税の利用を選択してからの累計となるので、特別控除となります。| 特別控除後の課税価格 | 税率 | 控除額 |
|---|---|---|
| 一律 | 20% | ― |
暦年課税制度と相続時精算課税制度を相続税の関係から比較すると…
この2つの制度を相続税の関係から比較するとどういった違いがあるのでしょうか。まず、加算対象となる贈与財産が違います。
暦年課税制度では、相続開始前3年以内に贈与された財産のみが加算対象となります。
一方相続時精算課税制度では、相続時精算課税を選択した年以降の贈与財産全てが加算対象です。
2点目の違いは、適用対象者です。暦年課税制度では、相続や遺贈により財産を取得した場合のみ適用となるのに対し、相続時精算課税制度では、たとえ相続放棄したとしても、適用対象となります。
生前贈与の節税対策ポイント
暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらが有効かについては、何を贈与するか、どのくらいの金額を贈与するかによって変わります。2つの制度のどちらを活用するか決めている方は、その特性を生かした贈与を行いましょう。例えば、暦年課税制度を活用したい場合は、
- 早い段階で贈与する(=3年以内の贈与は相続税の対象となるため)
- 将来、相続人にならない人に贈与する
相続時精算課税制度を活用したい場合は、
- 大きな金額を渡す
- 将来価値が上がる可能性のある資産を贈与する
死亡した時点での遺産額が課税対象の相続税は、遺産額やそれに基づく税金を自由に決めることができません。それに比べて贈与税は、どのくらい贈与するかを自由に決めることができますから、税負担を比較しながら毎年の贈与額を決定することができます。
相続税についてお悩みの際は、ぜひ一度弊社へご相談ください。
税理士法人NCPへのご相談はこちら
生前贈与に関するよくある質問
未成年の子・孫に贈与することはできますか?
暦年課税制度であれば、親権者の同意によって贈与することができます。
贈与は、あげた・もらったことの認識が必要ですが、それは口頭のみでも有効です。しかし、未成年の場合は贈与の事実を証明することが難しくなるため、贈与契約書等を作成し、親権者の署名押印とともに記録として残しておくことが大切です。
また、例えば未成年の孫が預金の贈与を受けた際、親が自由に使用してしまった場合、孫への贈与は認められなくなってしまいます。そのため、贈与で受け取った財産については、注意して管理することが必要です。
年間110万円以下の贈与の場合、申告は必要ですか?
申告不要で贈与税はかかりません。
家族や親戚以外に生前贈与することは可能ですか?
可能です。誰にでもいくらでも贈与することができます。
まとめ
生前対策として贈与を考えたときに、一概に贈与が節税となるわけではありません。相続税と贈与税のどちらで課税される方が有利なのか、贈与をした場合、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」のどちらが良いのかを十分検討してから実行することが大切です。今回だけの相続税対策を考えず、将来を考えた生前対策をおすすめします。
生前対策をお考えの方、相続税について相談したい方は、ぜひ税理士法人NCPにご相談ください。