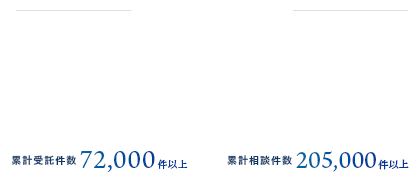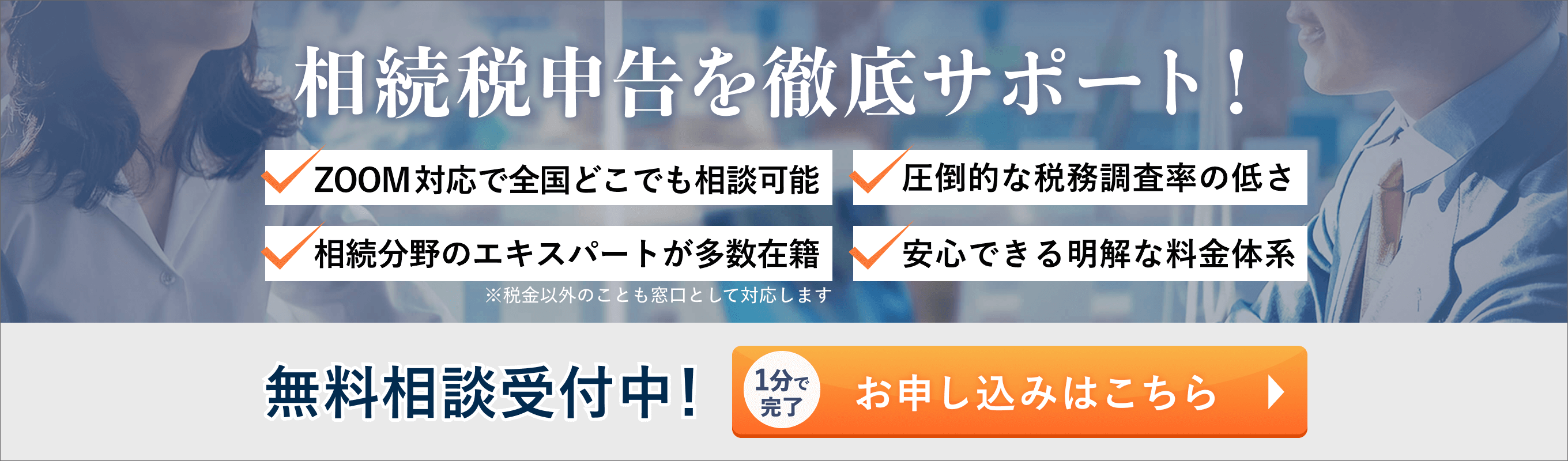相続税の税務調査とは?時期や対象となる人、調査対策について解説
2025.03.12
相続税は納税者が自ら税金を計算して申告・納付する「申告納税制度」が採用されています。
申告書を提出していなかったり、申告の内容に不備があったりすると、税務署から調査の連絡が来ることがあります。税務調査と聞くと不穏なイメージをもつ方が多いかもしれませんが、正しい知識をもつことで税務調査対策が可能です。
そこで今回は、相続税の税務調査についてご紹介します。相続税の税務調査の実態や、調査が対象になりやすい人の条件、税務調査に入られないための対策などもあわせて解説します。
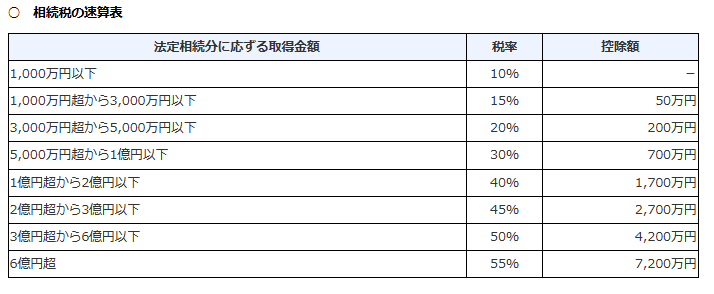 (国税局より引用)
(国税局より引用)
相続税の税務調査とは?
相続税の税務調査とは、国税庁が管轄する国税局や税務署などによって、相続人にあたる納税者が正しく税務申告を行っているかを調査することです。税額の計算ミスだけでなく虚偽申告の可能性もあるため、質問、検査などにより申告内容の確認が行われています。当然、相続税申告をしなければならない人が無申告の場合にも税務調査が行われます。税務調査の内容
税務署は、被相続人の財産に関わるさまざまな情報を把握できます。- 過去の所得
- 預貯金の流れ
- 不動産の保有状況
- 保険金の支払い状況
任意調査
任意調査とは、調査対象の人に対して事前に税務署から連絡があり、日時を決めて行われる調査のことです。 任意なので、納税者の同意を得て進められるのが前提ですが、納税者が税務調査への協力を拒否したり虚偽報告をしたりすると、罰則が適用される可能性もあるため、実際には拒否できるものではありません。 任意調査とはいえ、実質的には強制に近いものといえます。強制調査
強制調査とは、任意調査を拒否した人、脱税が疑われる人に対して行われる調査のことをいいます。 強制調査の場合、国税局の査察部(マルサ)が捜査令状をもって行うので、拒否はできません。 事前連絡は入らず、強制的に調査が行われます。とはいえ、相続税の場合は大半が任意調査で、強制調査が入ることはほとんどありません。税務調査はいつある?
税務調査の時期
相続税の税務調査は申告書を提出後すぐに行われるのではなく、申告書を提出した翌年、もしくはそのまた翌年に行われることが多いです。また、多くの場合、税務調査は8月から11月に行われます。相続税の時効は法定申告期限の翌日から起算して5年(悪質な場合は7年)のため安心できませんが、法定申告期限の翌日から3年以降に税務調査に入られる可能性は低くなるといえます。マルサは突然やってくる?
税務調査と聞くと、突然「マルサ」がやってくると思われるかもしれませんが、相続税の税務調査は税務署から事前に連絡があり、日程を調整した上で行われます。税務署からの連絡は、税理士に相続税申告を依頼していた場合にはその税理士宛に電話があります。税務調査の対象になりやすい人
税理士に頼まず自分で申告をした人
税理士に依頼せずに自分だけで申告書を作成した場合は、財産評価や税額計算、特例の適用が誤っている可能性が高く、税務調査が行われやすい傾向があります。相続税の申告をしなかった・漏れがあった人
相続税の申告義務があるにも関わらず申告をしなかった場合についても税務調査が入りやすくなります。配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例で税金がゼロになるケースがありますが、申告書を提出していなければ適用したことにはならないため、無申告になってしまいます。相続税申告に不慣れな税理士に依頼して申告をした人
税理士の多くは法人税や消費税、所得税をメインにしているところが多く、相続税申告に不慣れな税理士は相続税を専門にしている税理士に比べて申告内容の信頼性が薄い傾向にあります。遺産規模が大きい人
相続財産の金額が2~3億円以上になるなど、遺産規模が大きい場合、特に疑わしいことがなくても税務調査の対象になりやすい傾向にあります。 遺産規模が大きいぶん、財産評価や税額計算にミスが発生しやすくなります。また、申告漏れや納税漏れがあった場合に課される追徴税額が大きいということも関係しています。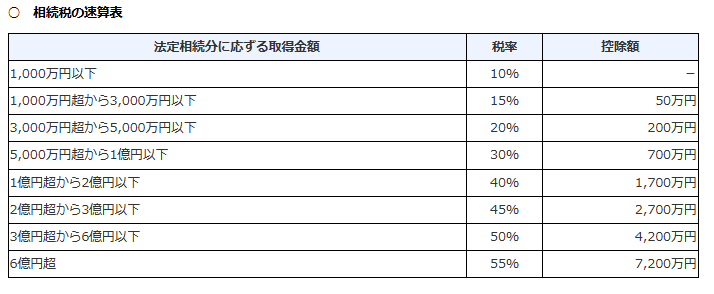 (国税局より引用)
(国税局より引用)
名義財産がある人
被相続人以外の名義で被相続人が拠出・管理していた預金や有価証券がある場合にも税務調査の対象になりやすいです。名義預金として財産計上することを避けるためには、財産をもらった本人が通帳を管理し、財産を自由に利用できる状態にしておくことが必要です。預貯金の移動が多い人
生前の預貯金の移動が多い場合も税務調査の対象になりやすいです。税務署は被相続人や相続人、親族の口座を10年遡って調べることができます。資金移動が多いと相続人や親族の口座に移しているのではないかと税務署が考えるかもしれません。税務調査を受けている人の割合
例年、税務調査率は12%程度でしたが、令和6年12月に公表された国税庁の資料によると、令和5年事務年度(令和5年11月~令和6年10月)の申告件数は155,740件、実地調査件数は8,556件で、税務調査率は約5.4%となっています。前年の税務調査率も5.4%のため割合は変動していませんが、実地件数及び追徴税額合計ではともに前年より増加(対前事務年度比104.4%、109.8%)しています。 参考:国税庁「令和5年分 相続税の申告事績の概要」 参考:国税庁「令和5事務年度における相続税の調査等の状況」税務調査に入られないための対策
財産状況を家族で共有しておく
被相続人の財産を遺族が把握していないために、相続税の申告漏れが起きる場合があります。家族が知らない預金口座や高価な収集品、知人とのお金の貸し借りなどです。そういった財産(もしくは債務)を見つけるのは非常に手間ですし、見落としてしまうおそれもあります。そのため、被相続人が生前のうちにどんな財産がどのくらいあるのかを家族で共有しておきましょう。 財産状況を家族に伝えることに抵抗がある場合には、財産リストを作成しておき、もしものときには財産リストを見るように伝えておくと良いでしょう。資金移動について証拠や記録を残しておく
先にも述べましたが、税務署は被相続人や相続人、親族の口座を10年遡って調べることができます。家族間でのお金の動きは把握され、行き先不明の大きな出金があれば税務調査のリスクが高まるおそれがあります。 家族間の資金移動について、贈与の場合は贈与契約書を作成するなど、証拠を残しておくと良いでしょう。証拠がないと名義預金を疑われてしまうかもしれません。 また、大きな出金があった場合は何のために引き出して使ったのかを記録し、タンス預金として手許に残しているのであればその旨も記録しておくと良いでしょう。いざという時に疑われること、分からないことを少しでも減らしましょう。税理士に相談する
正しく申告することが最重要なため、財産の計上漏れや計算ミスがないか注意しましょう。また、申告書の証拠となる書類をそろえることで、「申告漏れ」がない印象を与えられるかもしれません。 正しく丁寧な申告は、慣れていない方には非常にハードルが高いと思います。税務調査のリスクを低減させるために、相続専門の税理士に依頼されることをおすすめします。相続税の税務調査に関するよくある質問
税務調査ではどんな準備が必要ですか?
税務調査の前には、税理士などと調査中の対応や書類などを事前にすり合わせておきましょう。その際には、必要な書類や税務調査の流れ、そして対処方法を詳しく話し合うことがおすすめです。
税務調査の後に再調査はありますか?
相続税の税務調査は基本的には1回のみで、その後再調査ということはほぼないといえます。しかし、税務調査後に何かしら新しい情報が入った場合、再調査が行われる可能性はゼロではありません。
なお、相続税の申告・納税には期限があり、申告期限から5年(悪質な脱税等がある場合には7年)を経過した場合に時効を迎えるため調査の可能性はなくなります。
税務調査では立ち会いが必要ですか?
相続税は、調査の結果により追徴があった場合にはそれぞれの相続人に支払い義務が発生するため、相続人全員に立ち合いを求められることがあります。相続人全員の立ち会いが困難な場合でも、税務調査があるという連絡は必須です。