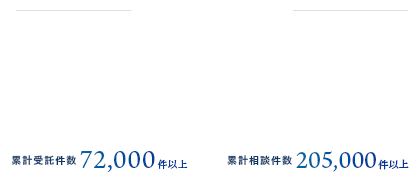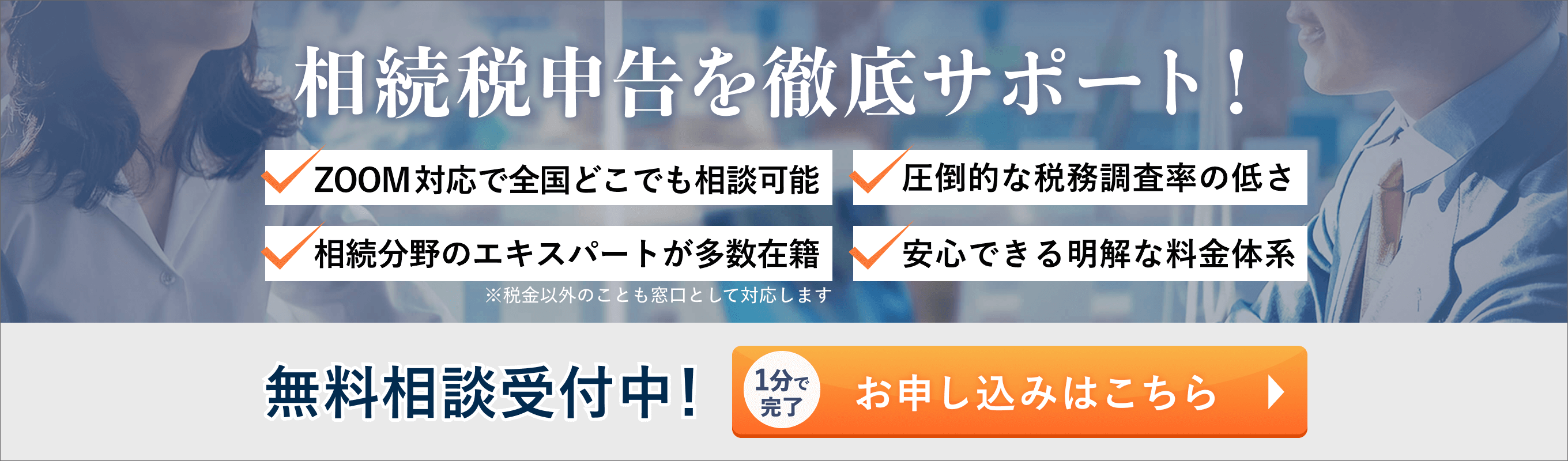相続税の債務控除とは?控除対象になる債務や対象者などを詳しく解説
2025.02.13
遺産を相続する際、預金や不動産などプラスとなる財産だけでなく、借金などの債務も引き継ぐことがあります。相続税を申告する際に、財産から債務を差し引いて計算できるのが「債務控除」です。
本記事では、控除対象に該当する債務と控除を受けられない債務、控除の対象外となる人や注意点などをご紹介します。
相続税の債務控除とは?
相続税の債務控除とは、相続財産の価額から、被相続人が残した債務や葬式費用を差し引くことをいいます。「債務」には、被相続人が生前残していた借入金や未払いの税金、医療費、預かり金等が含まれます。 債務控除により遺産総額から債務や葬式費用の金額を差し引くことで、相続税を下げることができます。 減税ができ納税者有利になるため、遺産相続に関わる方にとっては知識として知っておきたい情報です。相続財産から控除できる債務
まず始めに、どのような債務が相続財産から差し引けるものに該当するか解説します。借入金
被相続人が亡くなった時点における金融機関からの借入金、友人・知人から借りた個人の借金の残高が対象となります。 また、借入金に対する利息も被相続人が亡くなった時点での未払分は対象となります。未払金
被相続人の入院費や介護費など相続日以降に請求されたものや支払ったものが対象となります。 被相続人に課税された所得税や住民税、固定資産税などの未払税金や被相続人が生前に利用した公共料金で相続日以降支払いしたものも対象です。葬式費用
葬式の前後に発生した費用で、通常葬式に伴うと認められるものが対象となります。 具体的には、通夜・告別式に要する費用や埋葬、火葬、納骨などに要した費用などです。預かり敷金等
被相続人が賃貸不動産を所有しており、賃借人から敷金を預かっている場合には、債務控除の対象となります。相続財産から控除できない債務
続いて、相続財産から差し引くことができない債務をご説明します。団体信用生命保険の付された住宅ローン
団体信用生命保険とは、住宅の購入などのために金融機関から融資を受ける際に、債務者が加入できる生命保険契約です。 債務者が住宅ローンの返済期間中に亡くなった場合、団体信用生命保険が付されていれば死亡保険金により融資が完済され、相続人には融資を引き継がないため、債務として取り扱いません。墓地や仏壇などの購入代金の未払分
墓地や仏壇などは非課税財産のため、相続税はかかりません。そのため、墓地や墓石、仏壇などの購入代金や墓石の彫刻費用などの未払分は債務控除の対象外となります。葬儀用とみなされない費用
香典返し、初七日や回忌法要に要する費用、永代供養料は葬式費用として取り扱いません。 また、被相続人が生前に葬儀会社に対して支払いした互助会費も同様となります。保証債務
被相続人が他人の借入金の保証人となっている場合、保証債務は原則として債務控除できません。 ただし、主たる債務者が返済不能で保証債務者である被相続人が債務を負担しなければならなくなった場合で、かつ、主たる債務者に求償権を行使しても弁済を受ける見込みのない場合には、主たる債務者が返還不能と見込まれた部分の金額を債務として取り扱えます。債務控除を利用できない人
下記に該当する人は債務控除を受けることができません。相続放棄をした人
相続を放棄した人は、被相続人の財産を一切引き継ぎません。債務についても同様に被相続人の債務や葬式費用を引き継ぎません。 しかし、例外として相続放棄した人が遺贈(遺言による贈与)により財産を取得していた場合には、その人が実際に被相続人の葬式費用を負担した金額を差し引くことができます。制限納税義務者
制限納税義務者とは、相続または遺贈によって財産を取得した人のうち以下に該当する人を指します。- 国内に住所があり、在留資格を有しているが、相続開始日前15年以内において国内に住所を有していた期間の合計が10年以下の人
- 国内に住所がなく、日本国籍はあるが10年以内に日本に住所がない人
- 国内に住所がなく、日本国籍もない人
特定受遺者
特定受遺者とは、遺言によって特定の財産を引き継いだ人のことをいいます。 特定受遺者は、特定の財産のみを引き継ぐため、特定受遺者が支払いした葬式費用は債務控除の対象外となります。 しかし、包括遺贈(財産の特定をせずに一定の割合で行う遺贈)によって財産を取得した場合には、包括遺贈した割合分から債務控除をすることができます。債務控除を利用する際の注意点
債務控除によって相続税の税額を下げることができますが、マイナスの財産であることには変わりません。 もし、マイナスの財産が過大であった場合には、遺産を引き継ぐこと自体検討する方もいるでしょう。そこで、債務控除を利用する際の注意点をご説明します。債務控除適用後に相続財産が基礎控除額を超えるかを確認する
相続税の基礎控除額とは一定の割合で差し引きできる非課税枠で、3,000万円+(600万円×法定相続人の数)で計算された金額です。 相続が発生した際には、プラスの財産から債務控除分の財産を差し引いた金額が基礎控除額を超えなければ、相続税の申告は不要になります。遺産分割協議に影響を与える可能性がある
遺産分割協議では、債務や葬式費用を負担する人を決める必要があります。 多額の借入金などがある場合には、借入金の引き継ぎをめぐり遺産分割協議の過程でトラブルになる可能性が高いです。 また、未払金や葬式費用については、分割協議のタイミングでは既に支払いしていることが多くありますが、その負担を法定相続分で分けるなど遺産分割協議をした場合には、実際に支払いした人と遺産分割協議で負担をする人の間で精算する必要があります。 この場合には、支払いした金額や内容をメモなどで明確にしていなければ、トラブルに繋がることもあります。 トラブルを避けるため、マイナスの財産については誰が、いつ、何を支払いしたのかを記録しておくと遺産分割協議がスムーズに進められるでしょう。債務が大きい場合は他の選択肢も考える
被相続人の債務が過大にあり、相続自体をどうするか検討したい方もいるでしょう。 その場合には、相続放棄や限定承認を選択することが可能です。 相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法となります。 限定承認とは、プラスの財産の範囲内でマイナスの財産も引き継ぐ方法となります。 いずれの方法も相続の開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所にその旨を申告しなければなりません。 相続放棄や限定承認は期限があり、手続きが必要なものになるので、検討される場合には事前に情報を集めておくなど対策をしておきましょう。債務控除に関するよくある質問
債務控除を受けるために準備すべきものは何ですか?
債務控除を受けるためには、下記の書類が必要になります。
借入金…融資している金融機関より相続開始日現在の残高証明書
未払金…相続開始日以後に支払った医療費や介護費などの請求書・領収書
公租公課…相続開始日以後に支払った税金の領収書
口座引き落としの場合には、その年に届いた納税通知書
葬式費用…領収書・請求書
領収書が発行されない費用は、支払いした相手先や日付、金額を明記したメモ
借入金が共同名義の場合はどう扱われますか?
複数の債務者が同一の債務について、債務者がそれぞれ全部の弁済義務を負うことを連帯債務といいます。連帯債務の債務者のうち一人が被相続人の場合、相続人は被相続人の義務を承継することが原則となります。
連帯債務について、相続人同士で話し合い、負担する割合を決めることはできますが、債権者に対して負担する割合を主張することはできません。
そのため、被相続人の連帯債務を引き継ぎたくない場合には、相続放棄や限定承認を検討する必要があります。
控除対象外の費用にはどのようなものがありますか?
上述したように、団体信用生命保険の付された住宅ローン・墓地や仏壇などの購入代金の未払金・葬式費用に含まれないもの・保証債務は、債務控除の対象外です。また、以下の債務も控除対象外となるため、覚えておくと良いでしょう。
- 貸家などを所有している場合の前受賃料
- 火災保険料(前払いのため)
- 亡くなった後に支払いが発生するもの (遺言執行費用、相続税申告のための税理士報酬、相続登記のための登録免許税や司法書士業務報酬、戸籍収集のために支払う費用など)