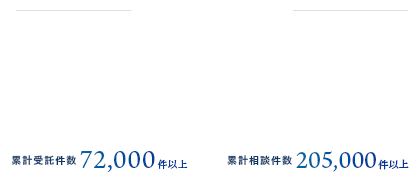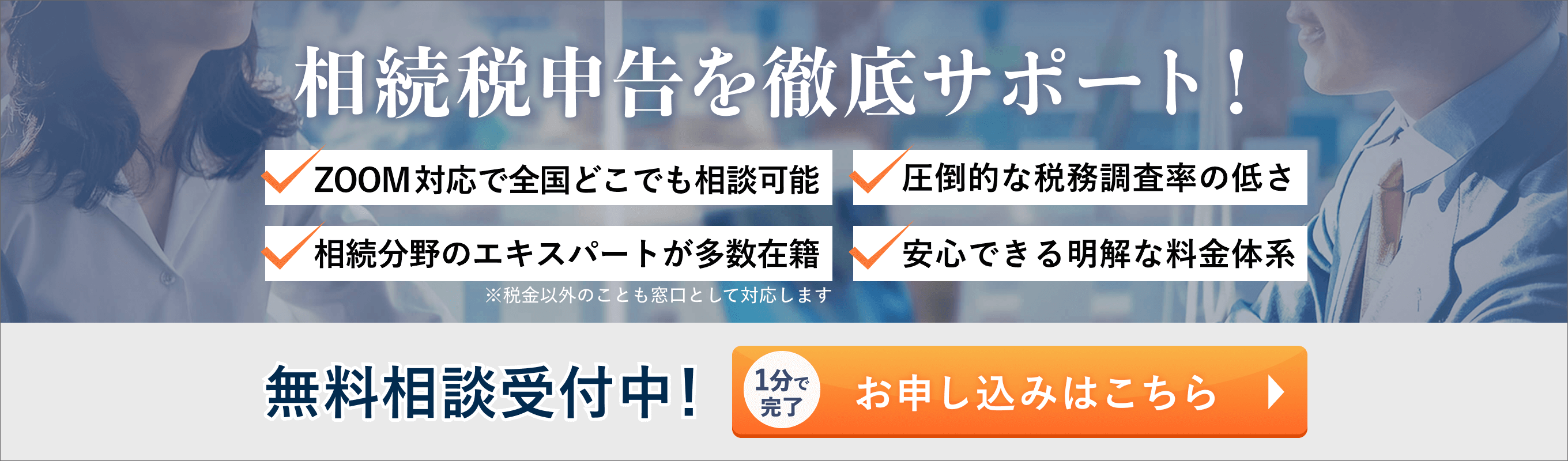小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等とは?適用要件や計算方法、注意点を解説
2025.04.08
相続税を評価するにあたり、特に複雑ともいわれているのが「土地」です。土地の評価を適切に評価することで、相続税を節税することができます。
相続開始の直前に亡くなった方が所有していた土地について、一定の要件を満たす場合に大幅な評価減が認められるのが、「小規模宅地等の特例」です。小規模宅地等の特例には4つの種類がありますが、今回はそのうちの特定事業用宅地等について詳しく解説します。
 引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)2 減額される割合等」
引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)2 減額される割合等」
 引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)3 特例の対象となる宅地等」
適用要件について、被相続人が花屋を営んでいた場合を例にとって考えてみます。
引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)3 特例の対象となる宅地等」
適用要件について、被相続人が花屋を営んでいた場合を例にとって考えてみます。
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等とは?
そもそも小規模宅地等の特例とは
小規模宅地等の特例とは、高額な相続税負担により自宅や事業用不動産を手放さなければならない相続人を配慮し、配偶者やお子様など残された家族が継続的に使用できるように設けられた特例です。一定の要件を満たす場合に50%又は80%の大幅な評価減が認められています。特定事業用宅地等とは
特定事業用宅地等とは、被相続人等が個人事業を営んでいたときの事業用の土地(例えば、事務所や店舗、倉庫など)のことを指します。小規模宅地等の特例を適用することにより、土地の評価額を80%減額できるため、相続税を節税できるというメリットがあります。事業のうち不動産貸付業等(アパート・貸駐車場など)については貸付事業用宅地等に該当するため50%減額となります。 関連コラム:「小規模宅地等の特例とは?土地の相続税が減額される適用条件を解説」特例の併用ができる
特定事業用宅地等に当てはまる場合、他の小規模宅地等の特例と併用することができます。事業用の土地のほか、自宅や貸駐車場などの土地も相続する場合などです。 どの特例と併用するかによって限度面積が異なってきます。 引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)2 減額される割合等」
引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)2 減額される割合等」
小規模宅地等の特例における特定事業用宅地等の適用要件
特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を適用するには、利用状況に応じてそれぞれ事業承継要件、保有継続要件という要件があります。 引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)3 特例の対象となる宅地等」
適用要件について、被相続人が花屋を営んでいた場合を例にとって考えてみます。
引用:国税庁「No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)3 特例の対象となる宅地等」
適用要件について、被相続人が花屋を営んでいた場合を例にとって考えてみます。
①被相続人の事業の用に供されていた宅地等
上記の表に当てはめると、事業継続要件は、取得した親族が申告期限までに「被相続人の事業」である花屋を引き継ぎ、且つ、その事業を申告期限まで継続して営んでいること、保有継続要件は、その宅地等を相続税の申告期限まで継続して保有していることです。 転業してしまうと特例の適用ができなくなりますので注意が必要です。 3年以内事業宅地等について 相続開始前の3年以内に新たに事業の用に供された宅地等(以下、3年以内事業宅地等)については、一定の規模以上(※)の事業に該当する場合を除き、特例の対象外となります。ただし、平成31年4月1日から令和4年3月31日までの間に相続又は遺贈により取得した宅地等のうち、平成31年3月31日までに事業の用に供された宅地等については、3年以内事業宅地等に該当しないものとする経過措置があります。②被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等
このケースでの事業継続要件は、取得した親族が被相続人と生計を一にしており、相続開始の直前から相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を「自らの事業」の用に供していること、保有継続要件は、相続税の申告期限まで引き続きその宅地等を保有していることです。 生計を一にしていた親族は「自らの事業」であれば良いので、カフェなど、他の事業へ転業することも可能です。(ただし、不動産貸付事業への転業は不可)。特定事業用宅地等を受ける取得者の適用要件
①の被相続人の事業の用に供されていた宅地等については、相続又は遺贈により取得した被相続人の親族のうち事業を承継する親族であれば、どなたが取得しても小規模宅地等の特例を適用可能です。 (事業を承継する者と宅地の取得者が異なる場合には適用不可) 一方で、②の被相続人と生計を一にしていた親族の事業の用に供されていた宅地等については、被相続人と生計を一にしていたその親族本人が取得しなければ、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。評価額の計算方法
限度面積と減額割合
限度面積と減額割合は以下の通りです。 限度面積:400㎡ 減額割合:80% 面積が400㎡を超える宅地の場合は、そのうちの400㎡までの部分に関して80%の減額が可能です。評価額の計算方法
- 宅地の評価額が1,000万円、面積が300㎡の場合 →300㎡≦400㎡のため、土地全体に対して減額することができます。 したがって、1,000万円×80%=800万円が減額となります。
- 宅地の評価額が1,000万円、面積が500㎡の場合 →500㎡≧400㎡のため、400㎡までが減額の範囲となります。 したがって、1,000万円×400㎡/500㎡×80%=640万円が減額となります。
特定事業用宅地等を相続した場合の申請手続き
特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要となります。相続税の申告書に、この特例を受けようとする旨を記載するとともに、いくつかの添付書類をつけて税務署に提出します。 必要な添付書類は以下の通りです。 ①被相続人の全ての相続人を明らかにする戸籍の謄本(コピー可) ②図形式の法定相続情報一覧図の写し(コピー可) ※①か②はどちらか一方だけでも可。 ③遺言書の写し又は遺産分割協議書の写し ④相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書に押印したもの) ⑤申告期限後3年以内の分割見込書 →申告期限内に分割ができない場合に提出が必要になります。 ⑥総務大臣が交付した証明書 →一定の郵便局舎の敷地の用に供されている宅地等の場合に必要となります。 参考:国税庁「(参考)相続税の申告の際に提出していただく主な書類2(5)」特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例を受ける際の注意点
特例を適用するには大きく分けて2点ほど注意点があります。相続税の申告が必要
特定事業用宅地等として小規模宅地等の特例の適用を受けるためには、相続税の申告が必要となります。また、相続税の申告は期限があり、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。上述したように、申告にあたっては必要な書類が複数あります。収集するのにもかなりの時間を要することがありますので計画的に集めていきましょう。要件を満たさない場合は適用されない
被相続人の土地を引き継ぐ人が、きちんと要件に当てはまっているかどうかも確認することが大切です。 特定事業用宅地等の特例は、そこまで要件は多くありませんが、被相続人の事業を引き継ぐ人と宅地を取得する人が別人のケースや、被相続人が生前に「生計が別の相続人」に事業を継承し相続が発生したケースなどは要件を満たされず、特例が適用されないので注意が必要です。事業相続や評価額は相続専門の税理士への相談がおすすめ
特定事業用宅地等の特例は、減額の割合が80%と大きいため、適用するかしないかで大きく評価額が変わってきます。しかし、事業承継が絡んでくることなど要件が複雑になっており、特例を適用した結果相続税がゼロになる場合でも、相続税の申告は必須です。申告の際には詳細な土地評価資料も必要となり、ご自身で評価を行うのは困難な場合が多いでしょう。煩雑な手続きをご自身でされるよりも、相続専門の税理士に一度ご相談されることを強くおすすめします。小規模宅地等の特例の特定事業用宅地等に関するよくある質問
被相続人と別居していた場合は、適用対象外となりますか?
被相続人の事業の用に供されている宅地であれば、適用されます。しかし、被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用に供されていた宅地は対象外になります(別居でも生計を一にしていると認められる場合は適用できます)。
被相続人が営んでいた事業用の土地が複数ある場合、全ての土地に特例が適用されますか?
特例には、限度面積の要件があります。保有・継続要件を満たしていることを前提に、特定事業用宅地等の場合は限度面積400㎡であるため、限度面積内であれば適用されます。
特定事業用宅地等に駐車場は含まれますか?
いいえ、含まれません。特定事業用宅地等の「事業用」とは、ご自身で事業を行うことであるため、事業用の自動車を止める駐車場は適用することができますが、いわゆる貸駐車場は対象外となります。不動産を貸している駐車場の場合は、「貸付事業用宅地」となります。