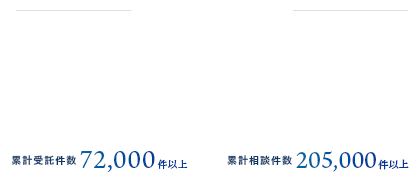生前贈与とは?相続税と贈与税の違いや生前贈与のメリット・注意点
2025.05.26
相続税は亡くなられた親などからの財産が相続人に受け継がれる場合にかかる税金ですが、財産が多ければ多いほど、その分相続税の負担も大きくなります。そのため、対策として生前贈与を検討されている方も多くいるでしょう。 しかし、贈与税の仕組みを理解していないと、贈与したとしても生前対策の効果が薄れてしまい、本来より多く納税してしまう可能性があります。 そこで今回は、相続税と贈与税の違いや生前贈与のメリット・デメリット、注意点などをご紹介します。
したがって、贈与は贈与をする人(以下、贈与者)の一方的な意志のみでは成立せず、贈与を受けた人(以下、受贈者)との間で、贈与の事実を認識している必要があります。
生前贈与を行うことで、贈与者の財産が減り相続税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、受贈者が一定の金額を超える財産を取得すると贈与税が課税されるため、贈与税の制度を正しく理解することが重要です。
贈与税の課税制度には、原則的な課税方式である「暦年贈与」と、一定の要件に当てはまる場合に選択できる「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに異なる課税方式を選択することができます。
複数の贈与者から贈与を受けた場合、各贈与者からの財産を合計した金額が課税対象となります。
税率は10%から55%までの超過累進税率となります。なお、税率は一般税率と特定税率の2種類あります。贈与より財産を取得した者が18歳(贈与受けた年の1月1日時点)以上で、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得したときは特例税率を使用し、それ以外の贈与は一般税率を使用して贈与税を計算します。
贈与者が異なるごとに暦年贈与と相続時精算課税どちらかを選択することができますが、一度「相続時精算課税」を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与課税」への変更はできませんので注意が必要となります。
相続時精算課税の税率は、贈与財産の累計額2,500万円(以下、特別控除額)までが非課税となり、特別控除額を超過した金額に対して一律20%の税率となります。
なお、税制改正により令和6年1月1日以降の贈与については、暦年贈与課税と同様の年間110万円の基礎控除額が新たに設けられました。
これにより、基礎控除額を差し引いた後の贈与財産の価額から特別控除額を超過した金額に対して一律20%の税率を乗じて贈与税を計算します。
相続税と贈与税は、どちらも財産を他人に移転する際に課税される税金です。相続税と贈与税の税率は10%~55%の超過累進税率と同じですが、下記の違いがあります。
相続により財産を取得した者が、被相続人から加算対象期間に暦年贈与課税により取得した財産があるときは、その者の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算します。
加算対象期間については、下記の通りです。
引用:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
相続時精算課税により財産の贈与を受けた者は、相続により財産を取得した場合でも取得しなかった場合でも、相続時精算課税により贈与を受けた財産(以下、相続時精算課税適用財産)の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。
なお、令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税にかかる基礎控除額110万円を控除した残額を加算します。
また相続時精算課税制度を利用して土地を贈与した場合、小規模宅地等の特例を適用することができなくなります。どちらが適しているか、それぞれのメリット・デメリットを理解し、十分検討しましょう。
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
国税庁ホームページに掲載されている父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与をした場合の税率(特例税率)の速算表をご覧ください。
速算表に記載の通り、贈与する金額が高いと税率も高くなります。
そのため、一括で多くの財産を贈与するよりも複数人に分散させて贈与をした方が受贈者の贈与税負担も軽減できます。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
そのため、将来価値の上昇が期待できる財産を生前に優先的に贈与することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
教育資金の一括贈与
教育資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき一括贈与を行った場合、受贈者は最大1,500万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用を受けるには受贈者が30歳未満であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件となります。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育てに必要な資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき一括贈与を行った場合、受贈者は最大1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用を受けるには受贈者が18歳以上50歳未満であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件となります。
住宅取得等資金贈与
受贈者が自己の居住用として住宅を新築、購入、または増改築に充てるために金銭の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用を受けるには受贈者が18歳以上であり、かつ贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(一定の家屋の場合には1,000万円以下)であることが要件となります。
また、上記の2つの制度とは異なり、適用にはその他の細かな要件が設けられています。
贈与税の非課税制度を活用する際は、詳細な要件を確認することが重要です。適用の可否については、専門家に相談の上、検討されることをおすすめします。
若いうちから早めに実施することで節税効果は高まりますが、贈与によって自身の生活費や介護費用が不足し、結果として子や孫に頼ることになっては本末転倒です。
そのため、贈与を計画する際には、老後の生活設計と併せて慎重に検討することが重要です。
税務上、定期贈与と認定されると単年ごとの贈与とされず、全体が一括で贈与されたとみなされる場合があります。定期贈与と認定されてしまうと、最初の贈与時点で全額を一括贈与したものとして贈与税の負担が大きくなる可能性があります。
定期贈与と認定されないためには、毎年異なる金額を贈与することや、贈与契約書の作成をして根拠となる書面を残すことなどが有効です。
そのため、贈与を行う際には、相続時精算課税制度の検討や贈与者の相続人とならない親族への贈与検討が必要となります。
生前贈与は、比較的手軽に行える相続税の対策の一つです。令和6年の相続時精算課税の税制改正により、相続税の節税対策への関心が高まっています。
しかし、ご自身で相続対策を判断し実行するのは容易ではありません。そのため、まずは専門家に相談し、現状を把握した上で適切な節税対策を検討されることをおすすめします。
相続専門税理士法人NCPでは、お客様からのご質問も迅速かつ細やかに対応いたしますので、ご相続でお悩み事がございましたらぜひ一度お問い合わせください。
生前贈与とは?
生前贈与とは、生きている間に自身の財産を無償で相手方に与え、相手方が受諾することを指します。したがって、贈与は贈与をする人(以下、贈与者)の一方的な意志のみでは成立せず、贈与を受けた人(以下、受贈者)との間で、贈与の事実を認識している必要があります。
生前贈与を行うことで、贈与者の財産が減り相続税の負担を軽減できる可能性があります。
ただし、受贈者が一定の金額を超える財産を取得すると贈与税が課税されるため、贈与税の制度を正しく理解することが重要です。
贈与税の種類
贈与税は、個人から財産を贈与された際に課される税金で、受贈者が納税義務を負います。贈与税の課税制度には、原則的な課税方式である「暦年贈与」と、一定の要件に当てはまる場合に選択できる「相続時精算課税」の2つがあり、贈与者ごとに異なる課税方式を選択することができます。
暦年贈与課税
暦年贈与課税とは、1月1日から12月31日までの1年間で受け取った贈与の財産額の合計から110万円の基礎控除額を差し引いた金額に、税率を乗じて贈与税を計算する方法です。複数の贈与者から贈与を受けた場合、各贈与者からの財産を合計した金額が課税対象となります。
税率は10%から55%までの超過累進税率となります。なお、税率は一般税率と特定税率の2種類あります。贈与より財産を取得した者が18歳(贈与受けた年の1月1日時点)以上で、父母や祖父母などの直系尊属から贈与により財産を取得したときは特例税率を使用し、それ以外の贈与は一般税率を使用して贈与税を計算します。
相続時精算課税
相続時精算課税とは、贈与した年の1月1日時点で60歳以上の父母や祖父母から、その年の1月1日時点で18歳以上の子や孫へ贈与した場合に適用できる制度です。贈与者が異なるごとに暦年贈与と相続時精算課税どちらかを選択することができますが、一度「相続時精算課税」を選択すると、その後、同じ贈与者からの贈与について「暦年贈与課税」への変更はできませんので注意が必要となります。
相続時精算課税の税率は、贈与財産の累計額2,500万円(以下、特別控除額)までが非課税となり、特別控除額を超過した金額に対して一律20%の税率となります。
なお、税制改正により令和6年1月1日以降の贈与については、暦年贈与課税と同様の年間110万円の基礎控除額が新たに設けられました。
これにより、基礎控除額を差し引いた後の贈与財産の価額から特別控除額を超過した金額に対して一律20%の税率を乗じて贈与税を計算します。
相続税と贈与税の違い
続いて、相続税と贈与税の違いを説明します。相続税と贈与税は、どちらも財産を他人に移転する際に課税される税金です。相続税と贈与税の税率は10%~55%の超過累進税率と同じですが、下記の違いがあります。
- 課税のタイミング
相続税は死亡による財産移転ですが、贈与税は生前の財産移転時です。 - 納税義務者
相続税は財産を取得する相続人・遺贈者ですが、贈与税は受贈者です。 - 基礎控除額
相続税は最低3,000万円あり相続人が1人増えるごとに600万円ずつ基礎控除額が加算されます。一方で贈与税は、財産額に関係なく受贈者1人につき年間110万円となります。
相続税における暦年贈与課税と相続時精算課税の違い
暦年贈与課税と相続時精算課税については、相続税における取り扱いが異なります。相続により財産を取得した者が、被相続人から加算対象期間に暦年贈与課税により取得した財産があるときは、その者の相続税の課税価格にその財産の贈与時の価額を加算します。
加算対象期間については、下記の通りです。
| 被相続人の相続開始日 | 加算対象期間 |
|---|---|
| ~令和8年12月31日 | ~令和8年12月31日 相続開始前3年以内(死亡の日からさかのぼって3年前の日から死亡の日までの間) |
| 令和9年1月1日~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から死亡の日までの間 |
| 令和13年1月1日~ | 相続開始前7年以内(死亡の日からさかのぼって7年前の日から死亡の日までの間) |
引用:国税庁「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」
相続時精算課税により財産の贈与を受けた者は、相続により財産を取得した場合でも取得しなかった場合でも、相続時精算課税により贈与を受けた財産(以下、相続時精算課税適用財産)の贈与時の価額を相続税の課税価格に加算します。
なお、令和6年1月1日以後の贈与により取得した相続時精算課税適用財産については、贈与を受けた年分ごとに、相続時精算課税適用財産の贈与時の価額の合計額から相続時精算課税にかかる基礎控除額110万円を控除した残額を加算します。
生前贈与の節税対策メリット・デメリット
暦年課税制度と相続時精算課税制度のどちらを使って贈与するのが有利になるのか、メリットとデメリットを比較して考えていきます。| 生前贈与 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 暦年課税制度 |
|
|
| 相続時精算課税制度 |
|
|
小規模宅地等の特例について詳しくはこちら
生前贈与を上手に活用するには
生前贈与を行うにあたって、どのように贈与をすると節税が見込めるか活用方法をご説明します。なるべく複数人に贈与する
贈与税は超過累進税率を採用しており、贈与する財産の価額が高ければ高いほど税率は上昇します。国税庁ホームページに掲載されている父母や祖父母から18歳以上の子や孫へ贈与をした場合の税率(特例税率)の速算表をご覧ください。
速算表に記載の通り、贈与する金額が高いと税率も高くなります。
そのため、一括で多くの財産を贈与するよりも複数人に分散させて贈与をした方が受贈者の贈与税負担も軽減できます。
参考:国税庁「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」
将来価値の上昇が期待できる財産を贈与する
先述の項目で説明しましたが、相続人が被相続人から受けた贈与の財産は、その贈与時の価額で相続財産に加算されます。そのため、将来価値の上昇が期待できる財産を生前に優先的に贈与することで、相続税の負担を軽減できる可能性があります。
直系卑属への贈与税の非課税制度を活用する
祖父母や父母から子や孫に対する贈与については、贈与税の非課税制度があります。贈与税の非課税制度について、簡単にいくつかご紹介します。教育資金の一括贈与
教育資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき一括贈与を行った場合、受贈者は最大1,500万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用を受けるには受贈者が30歳未満であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件となります。
結婚・子育て資金の一括贈与
結婚や子育てに必要な資金に充てるため、金融機関との一定の契約に基づき一括贈与を行った場合、受贈者は最大1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用を受けるには受贈者が18歳以上50歳未満であり、かつ前年の合計所得金額が1,000万円以下であることが要件となります。
住宅取得等資金贈与
受贈者が自己の居住用として住宅を新築、購入、または増改築に充てるために金銭の贈与を受けた場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。
ただし、適用を受けるには受贈者が18歳以上であり、かつ贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(一定の家屋の場合には1,000万円以下)であることが要件となります。
また、上記の2つの制度とは異なり、適用にはその他の細かな要件が設けられています。
贈与税の非課税制度を活用する際は、詳細な要件を確認することが重要です。適用の可否については、専門家に相談の上、検討されることをおすすめします。
生前贈与を行う際の注意点
続いて、贈与を行う際の注意点をご説明します。老後の生活費や介護費用を考慮する
生前贈与は、いつ発生するかわからない相続に備えるための節税対策として有効です。若いうちから早めに実施することで節税効果は高まりますが、贈与によって自身の生活費や介護費用が不足し、結果として子や孫に頼ることになっては本末転倒です。
そのため、贈与を計画する際には、老後の生活設計と併せて慎重に検討することが重要です。
定期贈与の扱いにならないように注意する
定期贈与とは、あらかじめ一定の金額や期間を定めて繰り返し贈与する契約のことを指します。税務上、定期贈与と認定されると単年ごとの贈与とされず、全体が一括で贈与されたとみなされる場合があります。定期贈与と認定されてしまうと、最初の贈与時点で全額を一括贈与したものとして贈与税の負担が大きくなる可能性があります。
定期贈与と認定されないためには、毎年異なる金額を贈与することや、贈与契約書の作成をして根拠となる書面を残すことなどが有効です。
相続時から7年以内の生前贈与には注意する
令和6年の税制改正により、相続税の計算において生前贈与された財産額が相続財産として加算される期間が延長され、相続開始前7年以内の贈与が課税対象となりました。そのため、贈与を行う際には、相続時精算課税制度の検討や贈与者の相続人とならない親族への贈与検討が必要となります。
生前贈与に関するよくある質問
最後に、生前贈与に関する質問を回答と共にいくつかご説明します。未成年の子や孫に贈与することはできますか?
贈与は契約ですので、贈与者と受贈者の双方の同意が必要です。未成年者は単独で契約ができないため、未成年者の法定代理人である親権者が代わって同意する必要があります。
そのため、未成年者の親権者が同意すれば、未成年の子や孫へ贈与することが可能です。
また、贈与税契約書を作成する場合には、贈与者と未成年者の親権者が調印することになります。
そのため、未成年者の親権者が同意すれば、未成年の子や孫へ贈与することが可能です。
また、贈与税契約書を作成する場合には、贈与者と未成年者の親権者が調印することになります。
年間110万円以下の贈与の場合、申告は必要ですか?
年間110万円以下の贈与については、贈与税の申告は不要です。
また、相続時精算課税を適用している場合も、贈与税の申告は不要となります。
ただし、申告は不要であっても、贈与契約書を作成するなど適切な証拠を残すことが重要です。これにより税務リスクを回避し、贈与の正当性を明確にすることができます。
また、相続時精算課税を適用している場合も、贈与税の申告は不要となります。
ただし、申告は不要であっても、贈与契約書を作成するなど適切な証拠を残すことが重要です。これにより税務リスクを回避し、贈与の正当性を明確にすることができます。
まとめ
今回は、生前贈与に関することを簡単にご説明しました。生前贈与は、比較的手軽に行える相続税の対策の一つです。令和6年の相続時精算課税の税制改正により、相続税の節税対策への関心が高まっています。
しかし、ご自身で相続対策を判断し実行するのは容易ではありません。そのため、まずは専門家に相談し、現状を把握した上で適切な節税対策を検討されることをおすすめします。
相続専門税理士法人NCPでは、お客様からのご質問も迅速かつ細やかに対応いたしますので、ご相続でお悩み事がございましたらぜひ一度お問い合わせください。