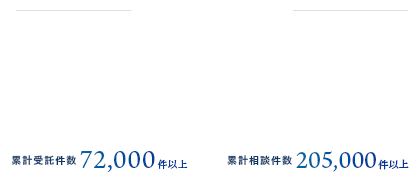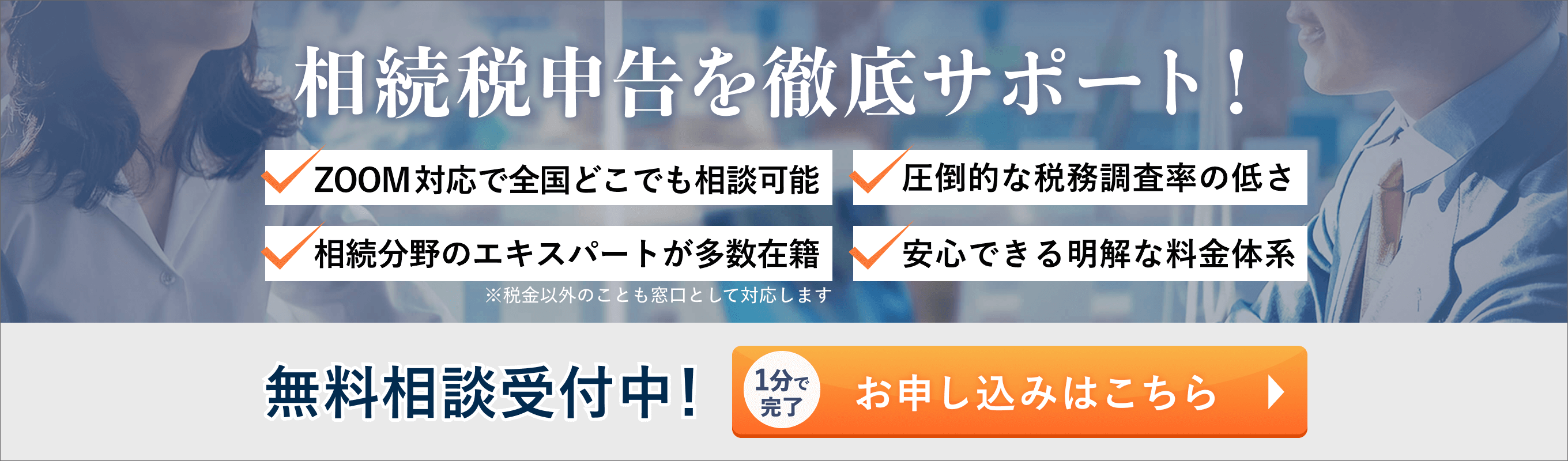市街地農地等とは?評価方法や評価明細書の書き方、注意点についてご紹介!
2025.04.08
市街地にある農地等を相続する際は、相続税がかかります。市街地農地等の相続税評価額を算出する際は、区分によって評価単位が異なるため注意が必要です。そこでこの記事では、市街地農地等の評価についてご説明します。
前半部では市街地農地等の概要や評価方法をご説明し、後半部では評価明細書の記載方法や評価の際の注意点、よくあるご質問への回答をご紹介します。
出典:令和6年分 宅地造成費の金額表(東京都)
出典:令和6年分 宅地造成費の金額表(東京都)
出典:令和6年分 宅地造成費の金額表(東京都)
傾斜度3度以下の土地については、「平坦地の宅地造成費」の額により計算します。
傾斜度については、原則として測定する起点は評価する土地に最も近い道路面の高さとし、傾斜の頂点(最下点)は、評価する土地の頂点(最下点)が奥行距離の最も長い地点にあるものとして判定します。
傾斜度の測定には、国土地理院の等高線図を用いて地図上で算出する方法や、現地調査で角度傾斜計やレーザー測量器を用いて確認する方法があります。
市街地農地とは
市街地農地とは、農地法上の宅地等への転用許可を既に受けた農地、あるいは転用許可を要しない農地のことを指します。 具体的には、以下に該当する地域のことをいいます。- 農地法4条または5条に規定する許可を受けた農地
- 市街化区域内にある農地
- 農地法等の規定により転用許可を要しないものとして、都道府県知事の指定を受けた農地
市街地農地と市街地周辺農地との違い
市街地農地等には、市街地農地と市街地周辺農地とが含まれることをご紹介しましたが、両者の違いをご説明します。 市街地周辺農地とは、未だ農地法上の宅地等への転用許可を受けておらず、転用に際し、転用許可を要する農地のことをいいます。 具体的には、以下に該当する農地のことを指します。- 第3種農地(都市的整備がされた区域内の農地または市街地にある農地)に該当するもの
- 第3種農地に該当する農地以外の農地のうち、近傍農地の売買実例価額、精通者意見価格等に照らし、第3種農地に準ずる農地と認められるもの
-
- 「比準」または「市比準」と記載がある場合…市街地農地
- 「周比準」と記載がある場合…市街地周辺農地
市街地農地等の評価方法
ここからは、市街地農地等の評価方法をご説明します。市街地農地等の評価単位
市街地農地等の評価にあたり、まずは評価単位を決定する必要があります。 評価単位は「利用の単位となっている一団の農地」とされていますが、ここでいう利用の単位とは、具体的には以下の通り判定するものと国税庁の質疑応答事例にて示されています。-
-
- 所有している農地を自ら使用している場合には、耕作の単位にかかわらず、その全体をその利用の単位となっている一団の農地とする。
- 所有している農地を自ら使用している場合において、その一部が生産緑地である場合には、生産緑地とそれ以外の部分をそれぞれ利用の単位となっている一団の農地とする。
- 所有する農地の一部について、永小作権または耕作権を設定させ、他の部分を自ら使用している場合には、永小作権または耕作権が設定されている部分と自ら使用している部分をそれぞれ利用の単位となっている一団の農地とする。
- 所有する農地を区分して複数の者に対して永小作権または耕作権を設定させている場合には、同一人に貸し付けられている部分ごとに利用の単位となっている一団の農地とする。
-
市街地農地等の評価方法の種類
市街地農地等が市街地農地と市街地周辺農地に区分されることは、既にご説明しましたが、それぞれの区分によって評価方法が異なります。 具体的には以下の通りに評価方法が分かれます。 <市街地農地の評価方法> 宅地比準方式または倍率方式 <市街地周辺農地の評価方法> 市街地農地であるとした場合の価額×0.8 市街地農地は、原則として宅地比準方式によって評価するものとされています。 ただし、市街化区域内の市街地農地については、地価事情の類似する地域ごとに国税局長が定める倍率が明示されている場合があります。その場合には、当該農地の固定資産税評価額にその倍率を乗じて計算する倍率方式によって評価することになります。 市街地周辺農地については、前述の通り、未だ転用許可を受けていない点を考慮し、市街地農地であるとした場合の価額の80%相当額に減額されます。宅地比準方式
ここでは、市街地農地の原則的な評価方法である宅地比準方式を解説します。 宅地比準方式の場合、以下の算式を用いて評価することとなります。 (その農地等が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額-1㎡あたりの造成費の金額)×地積 上記算式の「その農地等が宅地であるとした場合の1㎡あたりの価額」は、路線価方式により評価する地域であればその路線価をもとに計算します。倍率地域の場合は、近傍宅地(評価しようとする農地に最も近接し、かつ、道路からの位置や形状等が最も類似する宅地)の評価額(宅地としての固定資産税評価額×宅地としての評価倍率)を基準として計算します。造成費(宅地造成費)について
宅地比準方式の算式の構成要素である造成費(宅地造成費)についてご説明します。造成費(宅地造成費)とは
造成費(宅地造成費)とは、その農地等を宅地に転用する場合にかかる費用のことで、「1㎡あたりの造成費の金額」は、整地、土盛りまたは土止めに要する費用の額がおおむね同一と認められる地域ごとに定められており、国税庁のホームページで確認できます。 以下令和6年度の東京都を例にご説明します。造成費(宅地造成費)の工事項目
造成費(宅地造成費)の工事費目及びその内容は以下の通りです。 造成費の工事費目| 工事費目 | 内容 |
| 整地費 | 凹凸がある土地の地面を地ならしするための工事費または土盛工事を要する土地について、土盛工事をした後の地面を地ならしするための工事費 |
| 伐採・抜根費 | 樹木が生育している土地について、樹木を伐採し、根等を除去するための工事費(整地工事によって樹木を除去できる場合には、造成費に本工事費を含めません。) |
| 地盤改良費 | 湿田など軟弱な表土で覆われた土地の宅地造成にあたり、地盤を安定させるための工事費 |
| 土盛費 | 道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで搬入した土砂で埋め立て、地上げする場合の工事費 |
| 土止費 | 道路よりも低い位置にある土地について、宅地として利用できる高さ(原則として道路面)まで地上げする場合に、土盛りした土砂の流出や崩壊を防止するために構築する擁壁工事費 |
平坦地の宅地造成費
市街地農地等における造成費(宅地造成費)の金額は、平坦地と傾斜地の区分により異なります。 平坦地の造成費(宅地造成費)の金額は以下の通りです。 平坦地の宅地造成費| 工事費目 | 造成区分 | 金額 |
| 整地費 | 整地を必要とする面積1㎡あたり | 800円 |
| 伐採・抜根費 | 伐採・抜根を必要とする面積1㎡あたり | 1,000円 |
| 地盤改良費 | 地盤改良を必要とする面積1㎡あたり | 2,000円 |
| 土盛費 | 他から土砂を搬入して土盛りを必要とする場合の土盛り体積1㎥あたり | 7,500円 |
| 土止費 | 土止めを必要とする場合の擁壁の面積1㎡あたり | 82,000円 |
傾斜地の宅地造成費
傾斜地の宅地造成費の金額は、整地費、土盛費、土止費の宅地造成に要するすべての費用を含めて算定したものです。 以下の表の金額には、伐採・抜根費は含まれていません。そのため、伐採・抜根を要する土地については、「平坦地の宅地造成費」の「伐採・抜根費」の金額をもとに算出し加算します。 傾斜地の宅地造成費| 傾斜度 | 金額 |
|---|---|
| 3度超5度以下 | 21,700円/㎡ |
| 5度超10度以下 | 26,100円/㎡ |
| 10度超15度以下 | 40,900円/㎡ |
| 15度超20度以下 | 57,800円/㎡ |
| 20度超25度以下 | 63,900円/㎡ |
| 25度超30度以下 | 68,900円/㎡ |
市街地農地等の評価明細書の書き方
宅地比準方式の場合の市街地農地等の評価明細書の書き方を解説します。-
-
- 左側最上部にて、「市街地農地」、「市街地周辺農林」のうち該当する区分を選択します。
- 「所在地番」「現況地目」「①地積」に、評価対象地の情報を記載します。
- 「②評価額の計算内容」欄は、市街地農地等がa)倍率地域内かb)路線価地域内かに応じてそれぞれ以下の通り記載します。 a)倍率地域内の市街地農地等については、評価のもととした宅地の固定資産税評価額及び倍率を記載 b)路線価地域内の市街地農地等については、その市街地農地等が宅地である場合の計算内容及び評価額を記載
- 「④評価上考慮したその農地等の道路からの距離、形状等の条件に基づく評価額の計算内容」欄は、a)倍率地域内の市街地農地等について、位置、形状等の条件差を考慮した結果、③と⑤の評価額が異なる場合に記載します。b)路線価地域内の市街地農地等については、記載する必要はありません。
- 「宅地造成費の計算」欄にて、各国税局長の定めた「平坦地の宅地造成費」「傾斜地の宅地造成費」の金額をもとに、計算を行います。
-
市街地農地等の評価の際の注意点
市街地農地等の評価の際の注意点を解説します。現地調査を行う
評価対象地の宅地造成費を控除できるかどうか、宅地造成費の金額がいくらになるかは現地へ行かなければわからないので、必ず現地調査を行う必要があります。市街地山林の評価方法
市街地農地等から少し話が離れますが、市街地山林の価額は、宅地比準方式により算出します。 ただし、以下の2つの場合は市街地山林について宅地への転用が見込めないと認められ、評価方法が異なります。-
-
- その山林を宅地比準方式によって評価した結果、近隣の純山林の価額に比準して評価した価額を下回る場合
- その山林が急傾斜地等であるために宅地造成ができないと認められる場合
-
宅地への転用が可能か確認する
市街地農地等の評価にあたっては、宅地への転用ができるかどうかの確認を行うことも大切です。先に述べた市街地山林と同様に、市街地農地等の評価の際にも宅地比準方式が使えない場合があるため、必ず確認が必要です。市街地農地等に関するよくある質問
市街地農地等を転用する場合は手続きが必要ですか?
市街地農地を転用する場合、各市町村への農業委員会に届出を行う必要があります。この場合は、届出を行うのみで転用が可能となります。
市街化調整区域内にある農地を転用する場合には、各市町村への農業委員会を経由して申請を行い、都道府県知事から許可を得る必要があります。
詳細な手続きは各都道府県のホームページをご確認ください。
市街地農地等が特別警戒区域内にある場合も適用対象となりますか?
近年、土砂災害特別警戒区域の指定件数が増加していることを踏まえ、土砂災害特別警戒区域内にある宅地の評価にあたり、その宅地に占める土砂災害特別警戒区域内となる部分の地積の割合に応じて一定の減額補正を行うこととされています。
既にご説明した通り、市街地農地等については、原則的には宅地比準方式により評価することとされていますが、その農地等を宅地に転用するときには、宅地としての利用が制限されることで減価が生じます。そのため、市街地農地等が特別警戒区域内にある場合においても、減額補正の適用対象となります。
市街地農地等に新しく家を建てることは可能ですか?
農地法により、農地の転用には一定の制限がかけられています。上述した通り、市街地農地を転用する場合には届出が、市街化調整区域内にある農地を転用する場合には都道府県知事の許可を得る必要があります。そのため、市街地農地等に新しく家を建てる場合には、その区分に応じて農地転用のための必要な手続きを行う必要があります。