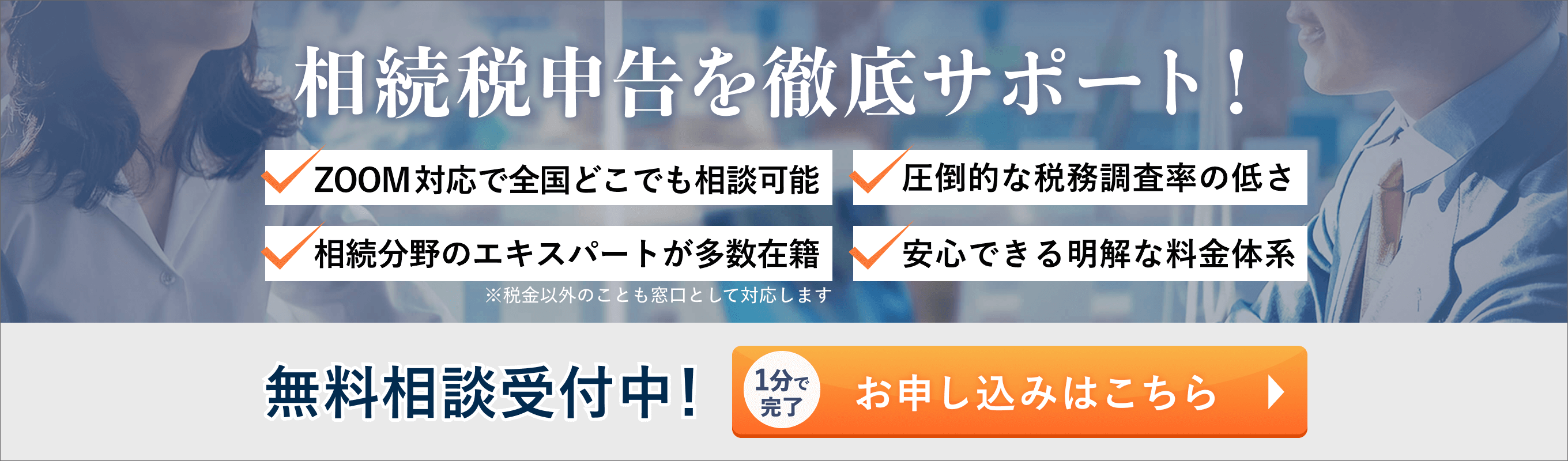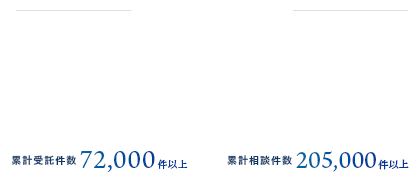小規模宅地等の特例の貸付事業用宅地等とは?適用要件や注意点を解説!
2025.07.09小規模宅地等の特例というと、被相続人(亡くなった方)の居住用不動産の土地が適用対象であるとイメージされる方が多いかもしれません。しかし、実は他人に貸付けている土地またはアパートの敷地についても、一定の要件を満たすと小規模宅地の特例の対象になることはご存知ですか?今回は、小規模宅地等の特例の対象となる貸付事業用宅地等について解説します。
貸付事業用宅地等とは?
貸付事業用宅地等とは、土地自体を第三者に貸したり、自分の土地の上あるいは借りている土地の上に自分で賃貸アパートを建てたりしている土地のことを指します。被相続人や被相続人と生計を一にしていた親族が不動産貸付事業に使っていた土地は、貸付事業用宅地等の特例の対象となります。
貸付事業用宅地等の特例の適用要件
貸付事業用宅地等の特例の適用には、利用状況に応じてそれぞれ以下のような要件があります。
被相続人の貸付事業用の宅地等の要件
相続又は遺贈により宅地等を取得した被相続人の親族が、被相続人の貸付事業を申告期限までに引き継ぎ、その宅地等を相続税の申告期限まで継続して保有し、且つその貸付事業を営んでいること
生計一親族の貸付事業用の宅地等の要件
相続又は遺贈により宅地等を取得した被相続人の親族が、被相続人と生計を一にしており、相続開始前から申告期限まで引き続きその宅地等を自らの貸付事業の用に供し、申告期限まで引き続きその宅地等を保有していること
上記どちらのケースにも共通して、相続税の申告期限までは相続又は遺贈された土地を保有し続けること、そして当該事業を続けることの2点が重要となってきます。
そのため、事業を継ぐ気はないからといって申告期限までに廃業したり、土地を売却したりすると小規模宅地等の特例対象から外れてしまうので注意が必要です。
また「被相続人の貸付事業用の宅地等の要件」に該当する場合は、相続又は遺贈により取得した被相続人の親族であればどなたが取得しても小規模宅地等の特例を適用可能です。
一方で、「生計一親族の貸付事業用の宅地等の要件」に該当する場合は、被相続人と生計を一にしていた親族本人が取得しなければ、小規模宅地等の特例の適用を受けることができません。また、その親族と被相続人との間に地代又は家賃の授受がないことも前提条件として必要となります。
限度面積と減額割合
貸付事業用宅地等の特例の限度面積は200㎡で減額割合は50%です。仮に300㎡の土地を相続する場合、貸付事業用宅地等の特例の要件を満たしても、200㎡に対しては、50%減額できますが、残りの100㎡に対しては減額できません。
平成30年度税制改正による影響
相続開始前3年以内に賃貸を開始した土地には適用できない
平成30年度の税制改正によって、平成30年4月1日から相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等については、貸付事業用宅地等の適用対象から除外されることになりました。つまり、平成30年4月1日以降に新たに貸付事業を開始した宅地等に関しては、3年以内に相続が発生してしまうと、小規模宅地等の特例を適用できなくなってしまったのです。
ただし、平成30年4月1日から令和3年3月31日の間に相続が発生した場合については、従来の通り、3年以内の貸付事業の開始であっても特例の適用対象となるという経過措置が取られていました。しかし、令和3年4月1日以降に発生した相続については、この経過措置の対象からも外れてしまうため、注意が必要です。
なお、例外として事業的規模、いわゆる「5棟10室基準」で本格的に賃貸事業が行われている場合には、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供した宅地等であっても引き続き適用することが可能です。
貸付事業用宅地等を適用するメリット
節税対策につながる
土地の評価額を最大で50%減額できるので、相続税の負担を軽減することができます。特に首都圏等の地価が高い不動産において、特例の適用を受けられるように生前から準備をしておくことは、相続税の節税において非常に有効です。
他の小規模宅地等の特例と併用ができる
貸付事業用の宅地等とは別に自宅を所有し、特定居住用宅地等の特例の適用要件を満たす場合には、特例を併用しそれぞれの宅地の減額が可能です。
併用する際の注意点は、それぞれの限度面積まで適用できるのではなく、以下の算式をもとに合計の限度面積が算出される点にあります。
限度面積の調整計算
特定居住用宅地等の面積 × 200/330 + 貸付事業用宅地等の面積 ≦ 200㎡
特定居住用宅地等に該当する宅地が82.5㎡、貸付事業用宅地等に該当する宅地が180㎡である例で、2パターンの計算を考えてみましょう。
- 特定居住用宅地等82.5㎡から優先して適用した場合は、算式に当てはめると、特定居住用宅地等につき82.5㎡、貸付事業用宅地等につき150㎡それぞれ特例の適用を受けられることになります。
- 貸付事業用宅地等180㎡から優先して適用した場合は、算式に当てはめると、貸付事業用宅地等につき180㎡、特定居住用宅地等につき33㎡それぞれ特例の適用を受けられることになります。
土地の単価の比較や遺産分割の方針によってもっとも有利に申告できるように注意する必要があります。
また、本コラムでは特定居住用宅地等の特例との併用を例に挙げましたが、その他の小規模宅地等の特例との併用も可能です。
貸付事業用宅地等を適用する際の注意点
アパートやマンションに空室が多い場合
空室に相当する部分には、原則として貸付事業用宅地等の特例は適用できません。ただし、貸付事業の用に供されていたアパートの1室について、相続開始の直前でたまたま入居者が立ち退き空室となっていた場合でも、新規の入居者を募集しており、いつでも貸付けできるように整備されているなどの状況であれば、被相続人等の事業は継続されているものと考えられます。この場合、空室に相当する敷地部分も含め、アパートの敷地すべてが貸付事業用宅地等に該当します(国税庁 措置法69の4-24の2)。
親族などに無償や格安で貸付する場合
相続人や親族に対して、無償で貸付ける場合や相場よりも安く貸付ける場合には貸付事業用宅地等の特例は適用できません。なぜなら、貸付事業用宅地等の特例の適用を受けるためには、”相当の対価を得て継続的におこなうもの“と認められる必要があり、上記のような場合にはこの”相当の対価“に該当しないこととなるからです。
駐車場へ適用する場合
駐車場に貸付事業用宅地等の特例を適用する場合は、駐車場として使われている土地の上に、構築物を設置する必要があります。構築物とは、アスファルト舗装、区画線、フェンス、機械装置(コインパーキングの精算機など)、砂利敷きをいいます。貸付事業用宅地等の特例の適用を受けるためには、“建物または構築物の敷地の用に供されている宅地等”と認められる必要があり、更地にロープを張っただけのいわゆる青空駐車場はこの要件を満たさないため、貸付事業用宅地等の特例は適用できません。
なお、砂利敷きについては、砂利が地中に埋もれていて、砂利は構築物とはいえない状態とされ特例の適用が認められなかった事例(国税不服審判所 平成7年1月25日裁決)があります。実際の申告にあたっては現地の確認をする等して、注意して判断する必要があります。
貸付事業用宅地等に関するよくある質問
貸付事業用宅地等を適用する際に必要な書類には何がありますか?
- 遺言書または遺産分割協議書(相続人全員の印鑑証明書付き)
- 貸付事業用宅地等が相続開始前3年以内に新たに被相続人等の特定貸付事業の用に供されたものであるときには、被相続人等が相続開始の日まで3年を超えて特定貸付事業を行っていたことを明らかにする書類
共有名義の貸付事業用宅地等の場合、特例はどのように適用されますか?
被相続人が共有持ち分として所有していた部分にのみ適用が可能となります。
なお、建物が共有の場合にも同様に、被相続人の所有している持ち分に相当した部分のみ適用が可能となります。
まとめ
貸付事業用宅地等の特例は、特定居住用宅地等の特例と併用することもできるため、正しく適用すれば大きな減税効果が見込めます。ですが、限度面積の計算や、どちらの特例を優先して適用していくか等、ベストな判断には正確な理解が必要になりますので、まずは一度土地評価に詳しい専門家にご相談することをおすすめします。相続専門の税理士法人NCPでは、土地評価に精通した税理士が在籍しており、ノウハウがございますのでぜひ一度ご相談ください。