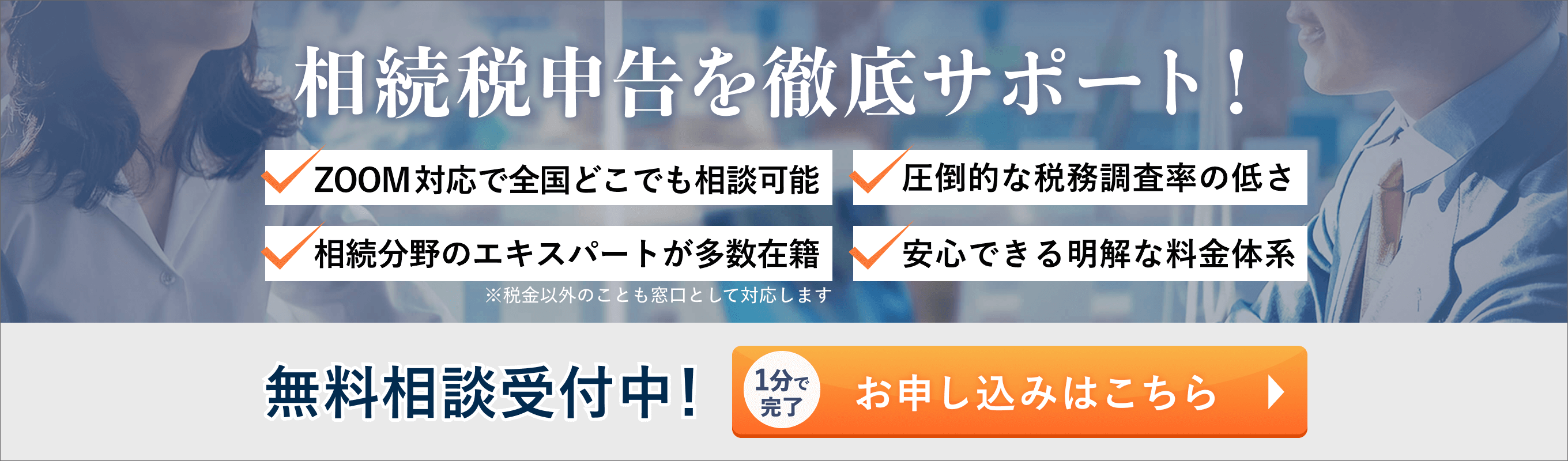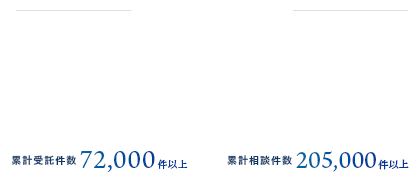公社債とは?相続税評価額の計算方法をパターン別に徹底解説!
2025.07.24公社債は、株式投資に比べるとリスクが低く、安定した利子等を得られることから、投資家からの人気を集めています。しかし、相続税評価額の計算は、複雑で多岐にわたります。そこで今回は、公社債の種類に応じた、評価方法をご紹介します。
公社債とは?
公社債とは、国や地方公共団体、事業会社などが一般投資家から資金を調達するために発行する有価証券です。上場株式とは異なり、発行者に利益が出ていなくても、一定期間ごとに利子を受け取ることができます。
公社債の種類に応じて評価方法が異なるため、それぞれ見ていきましょう。
利付公社債の相続税評価方法
利付公社債とは、一定期間ごとに利子が支払われる債券です。
上場している利付公社債
課税時期の最終価格に、受け取っていない既経過利息(源泉徴収控除後)を加算して、評価額を求めます。
なお、最終価格は「東京証券取引所日報」で、確認ができます。
また、課税時期に最終価格がない場合(市場休業日)は、もっとも近い市場営業日の最終価格を採用します。
売買参考統計値のある利付公社債
その銘柄の課税時期における、平均値により評価額を求めます。
なお、売買参考統計値は「日本証券業協会」から、確認ができます。
その他の公社債(外国債券など)
上場している利付公社債と売買参考統計値のある利付公社債以外の利付公社債については、「発行価額」を用いて評価額を求めます。
なお、外国債券とは、発行体・通貨・発行市場のうち、いずれかが日本国内以外である債券となります。
外国債券については、日本の債券と同じ方法で評価額を計算します。具体的には、外貨ベースで計算をし、最後に円貨換算をします。
個人向けの国債
国が個人向けに発行するもので、満期前であっても換金することができます。
なお、評価額の計算にあたっては、財務省の「中途換金シミュレーション」から確認ができます。
割引公社債の相続税評価方法
割引公社債とは、額面金額から割引されて発行される公社債です。券面額と発行価額との差額(償還差益)が利子に相当する部分にあたります。
上場している割引公社債
下記の通り、評価額を求めます。
利付公社債と同じく、最終価格は「東京証券取引所日報」で、確認ができます。
その他の割引公社債
上場している割引公社債と売買参考統計値のある割引公社債以外の割引公社債は、下記の通り、評価額を求めます。
転換社債の相続税評価方法
転換社債とは、「転換社債型新株予約権付社債」の略称で、事前に決められた価格(転換価格)で、発行企業の株式に転換できる権利が付与されています。
また、債券としての安定性と、株式としての収益性の両方を兼ね備えているため、投資家にとって魅力的な選択肢であると言われています。
相続税評価額については、利付公社債と同じ方法で求めます。
なお、転換社債の発行会社の株式価額が、その転換社債の転換価格を超える場合については、次の算式により計算した金額によって評価します。
公社債を相続する場合の注意点
公社債を相続する場合、以下の注意点があります。
相続税評価は時間や手間がかかる
公社債の相続税評価額の計算は、公社債の種類、どの評価方法を適用して計算するかといった、判断が必要になります。
特に、外国債券などの場合には、為替換算などの複雑な計算が必要なため、手間もかかります。
公社債は相続人全員の準共有財産となる
公社債は遺産分割の対象になります。よって、遺産分割協議が成立するまでは「準共有」の状態となり、単独で売却や名義変更を行うことができません。
まとめ
今回は、公社債の評価についてご紹介しました。公社債の評価には、公社債の種類、上場の有無といったさまざまな判断が必要になります。適正な評価額を計算するためには、公社債の評価に精通した税理士にご相談することをおすすめします。
相続専門の税理士法人NCPは、相続対策に強い経験豊富な税理士が相続税申告・相続手続き・遺言作成・生前対策をサポートします。